警察学校での実体験をもとにお送りする【実録警察学校】シリーズの第2話です。
第1話は下記のリンクからご覧ください。
前回はいよいよ警察学校入校の日を迎え、入校早々にして同期生が退職する波乱の幕開けでした。
様々なカルチャーショックを受ける中、次々と警察学校の洗礼を受ける展開が続きます。
サラリーマンを退職し、警察学校という特殊な世界で生きていく様子をお楽しみください。
入校式で洗礼を受ける
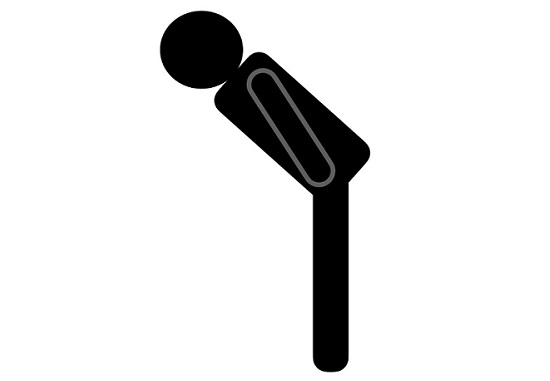
入校者が次々と教官に怒鳴られる流れが続いたが、なんとか全員教官への申告が終わり、着席した。
依然、鋭い眼差しの教官たちが初任科生を取り囲んでおり、異様な雰囲気は変わっていない。
このとき、既に脱落者(退職者)が1名。
警察学校に到着してわずか1時間での話である。
もっと厳密に言えば、警察官としてキャリアをスタートさせて1時間足らずの出来事だった。
いきなりの衝撃展開で誰もが動揺をしていただろう。
警察学校で退職する者が多いというのはある程度聞いていたが、それにしても早すぎる。
私はこのあと何が行われるのか、この先どうなるのかということで不安で仕方なかった。
入校の申告を終えて全員が着席すると、警察学校の幹部から説明があった。
このあとは入校式が行われるとのことだった。
警察学校には卒業式があれば入校式もある。
普通の学校でいえば入学式のようなものだ。
入学式といえば晴れやかな舞台であるが、警察学校の入校式はそんなものではない。
異様な雰囲気の中で行われるものだから想像がつきやすいはずだ。
余談だが、私が所属していた県警の警察学校は今では入校式に親も参加し、和やかな雰囲気で行われるようになったらしい。
映像も拝見したが、当時を考えればすごい変わりようだ。
入校した当日に簡素に入校式まで終わらせたことはすごく特殊な経験だったのだろう。
警察には色々な独自の礼式がある。
このとき行われた入校申告というのも警察礼式の1つだが、警察官はその場に適した礼式をしっかりこなしていく必要がある。
代表的なものが敬礼だ。
警察官の敬礼は誰もが知っている肘を伸ばす形の敬礼(制帽を被っている場合)だけでなく、制帽を被っていない場合の敬礼のやり方も決まっている。
敬礼以外にも「気を付け」や「右向け右」など、その1つ1つに角度やタイミングが決まっており、警察学校ではこの動作を完璧に覚えなければいけない。
これらの礼式は警察署に赴任してからも使う機会が多いので、警察学校で体に叩き込んでおく必要がある。
そして、警察学校の入校式は警察本部の本部長も出席する非常に重要な式典である。
一般的な警察官だと、本部長の顔が見れる機会は警察学校の入校式と卒業式くらいかもしれない。
それくらい本部長というのは雲の上の存在である。
そのため、当然ながら入校式は厳格な雰囲気の中で行われるし、警察礼式もきっちりこなさなければいけない。
本部長が出席する式典でダラダラすることや礼式に失敗することは許されないからだ。
しかし、私たちは警察学校に入校してわずか1時間が経ったばかりであり、いきなりそんなことができるわけがない。
一応、その場で敬礼の仕方や頭を下げるタイミング、角度などは教えてもらったが、ぎこちない動きでしかないし、全員のタイミングもバラバラ。
入校して1時間ならこれくらいが普通であるものの、当然ながら教官たちは怒声を響かせるのである。
「何回教えればできるんだ!!こんなに出来の悪い奴ら初めて見たぞ!!」
これはもはや警察学校の決まり文句であるが、私たちからすると少しショックを受けるものでもあった。
そんな状況だが、入校式の開始時間が迫っている。
できないけどやるしかない。
ここでは言われたことに従うしかないのだ。
ぎこちない入校式を終える
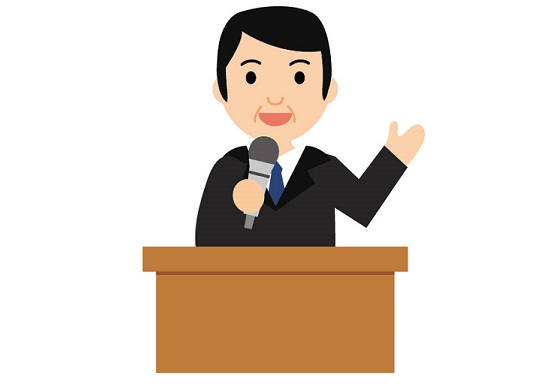
入校式の時間がやってきた。
警察本部の本部長をはじめ、県警の幹部たちも参列していた。
もちろん壇上に座っている人たちがどれだけ偉い人たちなのかはこのときまったくわかっていない。
ただ、明らかに偉そうな人たちが並んでいるし、ひとまず重要な式典であるということくらいは理解できていた。
入校式の流れとしては壇上に座っている幹部たちから祝辞を述べられ、その度に起立→敬礼を繰り返すというのが基本だった。
入校式が始まる前に起立や敬礼については少し練習をしていたが、これらは全員でタイミングを揃えるのが原則。
こういった場では特に一人のタイミングが遅れるだけで全体が緩く見えてしまう。
当然ながら、少し練習をしたくらいではタイミングを揃えることはできない。
言ってしまえば、ぎこちない入校式であったことは間違いないだろう。
本来なら本部長が出席する式典でそんなことが許されるわけないのだが、当時は特別だった。
今考えてもなぜこんなスケジュールだったのかは疑問だ。
それでも全員がなんとなくそれっぽい動きで乗り切り、なんとか入校式を終えた。
入校して最初の一大イベントが終わった。
ほっとするのも束の間、ガラッと雰囲気は変わり、またも講堂は異様な空気に包まれた。
入校式が終わったくらいで一息つく暇もない。
入校式では教官が声を荒げることはなかった。
さすがの教官たちも本部長をはじめとする幹部がいる前ではそういったことはしない。
だから入校式が終わった瞬間に異様な雰囲気へと戻ったのだ。
そんな異様な雰囲気の中、教官から次の指示が出た。
「教場に移動する」との指示だった。
突然このようなことを言われても私たちはどのように行動すればいいかはわからない。
なぜなら教場がどこにあるのかも知らないし、どうやって移動するのかもわからないからだ。
おどおどする私たちを見た教官がすかさず怒鳴ってくる。
「なにをゆっくりしとるんだ!早く整列しろ!」
入校初日の警察学校の教官は恐らく警察学校の生活の中でも一番怖いだろう。
とにかく初任科生に恐怖を植え付けようとするので、怒鳴るときのパワーが半端じゃない。
普通に考えればこれだけ怒られるのは異常だが、警察学校はこういうものだ。
入校当初耐えるしかない。
入校して数時間でこの世界の理不尽さはよくわかった。
まだまだ心の中は動揺していたが、次の予定へと移ることとなった。
教場に案内され、教官の自己紹介が始まる

講堂での入校式をなんとか終え、私たちは教場へと移動した。
「教場(きょうじょう)」とは一般的な学校でいうところの教室である。
警察学校では教室のことを教場と呼んでいる。
授業が行われるのはこの教場だし、自分たちにとっての教室でもある。
卒業までなにかと過ごすことが多いので、警察学校において特に思い出深い場所だ。
また、教場という言葉はドラマにもなったことで一躍有名になったことが記憶に新しい。
教場に入ると座席表が入り口の扉に張り出されていたので、その座席表に従ってそれぞれが着席した。
もちろんこの間も教官たちが付きっきりで目を光らせている。
緊張感から逃れることはできない。
「今からなにを行うのか」
警察学校に入校して数時間だが、まだまだ頭の中はこんな不安な気持ちでいっぱいである。
自分の学生番号を発見し、指定された座席へ着席した。
覚えておいて欲しいことは警察学校の教場にはいくつかの決められたルールがあることだ。
整理整頓に心がけて綺麗に使うことは当然だし、授業が終わった後に教場当番がホワイトボードを消しておくのも当然。
一般的な学校でやってきたことは当たり前のように率先して行う必要がある。
そして、それよりも大事なルールは授業が始まるときは担当者が教場の外に立って教官を出迎えるというもの。
警察学校では教官が自ら教場の扉を開けることはない。
教官に自ら扉を開けさせることは失礼にあたるというのが警察学校での常識だ。
では、教官はどのようにして教場に入ってくるのか。
当時は教官が教場に入室する際はドアマンが扉を開けることが絶対のルールとなっていた。
だから、授業が始まる時間になったらドアマンを担当する者が1人で教場の外に出て、教官が来るを扉の前で待つというのが決まりだった。
そして、教官が現れたタイミングでドアを開け、教場に入ってもらうのである。
これだけなら何も難しいことではないのだが、ドアマンの役割は扉を開けるだけではない。
教官が教場に入ってくるときには全員が起立した状態でないといけないというルールもあった。
どうやってそのタイミングを計るのか。
これがドアマンのもう1つの役割だが、教場の中で座っているクラス員に教官が来たことを告げるため、ドアマンは教官の姿を見たら「よろしくお願いします!!」と大きな声であいさつをする必要がある。
このあいさつが号令となり、教場の中にいるクラス員が一斉に起立をする流れになる。
当然、教場内にいるクラス員にあいさつが聞こえるようにする必要があるので、ドアマンが発する声の大きさは重要である。
このルールについては教場に到着してからすぐに説明を受けた。
そして、担任教官が間もなく教場に来るということで、早速1人の者がドアマンに選ばれ、外で待機することとなった。
ドアマンに指名されたのは扉のすぐ近くに座っていた者だった。
選ばれた理由はただ単にドアに近かったから。
このようにして警察学校では急に役割を振られることが多いので、常に心の準備はしておかなければならない。
このときに限ったことではないが、教官が教場にやってくる状況というのは今でも鮮明に覚えている。
警察学校はチャイムが鳴れば校内が静寂に包まれるため、実はドアマンのあいさつを聞かなくても教官が来たことはわかる。
それは教官の足音が静寂の中で響くからだ。
入校初日のこのときもそうだった。
校内が静まり返る中、明らかに足音が聞こえてくる。
しかもこの足音を響かせる人物が自分たちの教場に向かっていることが明らかだった。
そう、足音の正体は紛れもなく担任教官だ。
するとドアマンは教官の姿が見えたのだろう。
「よろしくお願いします!」
ドアマンが威勢よくあいさつした。
”担任教官が教場に入ってくる”
瞬間的にこう察知した私たちは勢いよく起立した。
しかし、聞こえてきたのは教官の怒鳴り声だった。
「てめぇ、そのあいさつはなんだ!!!聞こえん!!」
ドアの外でドアマンが盛大に怒られていた。
ドアの向こうでの出来事なので一切状況は見えていないが、教官が激怒している様子ははっきりと分かった。
初日ということもあり、全員が当たり前のように緊張している。
しかもいきなりドアマンを命ぜられ、思うように大きな声が出せないのは誰もがわかりきっている。
私はこのときも思った。
「理不尽だ…」
しかし、警察学校ではこれくらいが当たり前である。
理不尽に怒られるのが日常。
この後も教官とドアマンのそんなやり取りが続き、ようやく担任教官が教場に入ってきた。
担任教官が壇上に立ったところで、全員で頭を下げながら「よろしくお願いします」と大きな声であいさつをした。
なんとなくわかっていたが、教官は「声が小さい!!やり直せ!!」と勢いよく怒った。
このやり取りは3回くらい続いただろうか。
教官が納得することはなかったが、なんとか着席することを許された。
担任教官は斎藤(仮名)と名乗った。
どうやらバリバリの刑事課出身の人で、他の教官と比べても明らかに雰囲気が怖かった。
そして、斎藤教官は私たちを睨み付けるようにして堂々と言った。
「俺が担任をやるからには全員卒業させない。1人でも多く辞めさせるのが俺の仕事だ。全員が卒業できると思うなよ」
あまりにも強烈すぎる言葉だったが、座っている私たちはただうなずくしかなかった。
真剣な表情でそう語る斎藤教官に対し、恐怖を感じたのは言うまでもない。
その後、副担任教官などのあいさつもあり、この場は終了した。
このとき、時間にしてちょうどお昼の時間だった。
次は食堂で昼食をとるとのことで、みんな揃って食堂に移動した。
食事がのどを通らない…

ようやく昼食の時間となったが、ここまではずっと緊張感が続いている状態だった。
しかも単なる緊張感ではなく、今までに経験したことがないくらいの緊張感だから余計に疲れる。
時間の感覚もよくわからないままであり、既に精神的に疲れが出ていたくらい。
ひとまず昼休憩ということだが、はっきり言って食欲はない。
しかも、当然のごとく昼食を食べる際も私たちの周りでは教官が目を光らせている状況。
こんなにも監視をされながら食事をとるのは人生で初めてだったかもしれない。
食事の時間だからといってリラックスができるわけではなかった。
そんな中、教官からは「10分以内で食え」との指示が下った。
もともと私は食事を早くとるのが苦手だったし、大食いのタイプでもない。
さらにこのときはお腹も空いていない状態だった。
しっかり栄養のバランスが考えられた食事を目の前にしたが、まったく食が進まなかった。
横目で周りを見ると、私と同じように困っている様子の者が何人もいた。
この状況でもガツガツ食事がとれる人は立派な精神力だろう。
しかし、これだけ食欲がなくても10分以内に食事を終わらせなければいけない。
教官たちも容赦なく「早く食え!」と喝を入れてくる。
苦しかったが、無理矢理に口に詰め込むしかない。
こんなに苦しい食事をとることは人生初だったかもしれないし、味なんてものは感じなかった。
正直に言えば、このときなにを食べていたかも記憶が定かではない。
食事の時間は本当に10分で打ち切られた。
完食できなかった者もたくさんいた。
食事中でも「警察学校ってやばいな…」ということは何度も思ったし、たかだか食事1つにしても警察学校の洗礼を浴びる結果となった。
食事の後は寮に移動して荷物の整理を行うよう指示があった。
生活に必要な大型の荷物は事前に警察学校に向けて発送しており、前日までに先輩たちが各部屋に運んでくれていたらしい。
ちなみに私たちはこの日(10月)が警察学校入校の日であったが、すでに4月から警察学校に入校している高卒の先輩がおり、生活に関する細かいことなどはこの先輩たちが教えてくれた。
寮で荷物の整理をするときも先輩が手伝ってくれた。
先輩と言っても下は18歳から上は30歳まで幅広い。
私は26歳であったが、相手が18歳であろうが先に警察学校に入った者が先輩である。
なので、私たちは18歳の先輩に対しても礼儀をわきまえなければいけないし、人によっては18歳でも偉そうにしてくる先輩はたくさんいる。
18歳の先輩に「お前らしっかり声出せよ」と言われたこともあるし、これくらい当たり前だ。
とにかく先に警察官になった者が絶対的な先輩であり、1日でも早く警察学校に入校していればそれだけで先輩になる。
これが警察の世界なのである。
明日以降の動きについて説明を受ける

荷物整理の時間は先輩たちと一緒に行動をしており、教官はその場にいなかった。
わずかではあるが、ほっとできる時間だった。
先輩からは警察学校での生活面について主に指導を受けた。
警察学校はタイムスケジュールがしっかり決まっており、時間通りに行動しなければいけない。
それは食事であったり、掃除であったり色々ある。
翌日からは警察学校の朝の動きも覚えなければいけないし、先輩から教わることは多かった。
また、朝と夜には警察学校に入校している者全員が集合し、点呼が行われる。
このときの動きについても説明を受けた。
寮の部屋は5人の大部屋だった。
簡易的なベッドとクローゼットがあるところが個室になっており、寝るときだけは1人になれるという部屋だった。
当時、警察学校の寮が新築されたばかりだったので、寮とは思えないほど綺麗だった。
トイレや洗面台も非常に綺麗だったので、環境面で恵まれていたことは間違いない。
そして、このときようやく同期生と初めて会話をする機会ができた。
ここまでは私語をする機会が一切なく、誰が誰だかまったくわからない状況だったが、なんとか同部屋の者だけは会話をすることができた。
荷物整理の時間は1時間半くらいだっただろうか。
再び教場に戻るよう指示があった。
ここからはすべて集団行動である。
どこに移動するにもクラス全員で移動するよう指示され、たかだか寮から教場に戻るだけでも全員で揃って向かうのである。
警察学校の生活で大変なことの1つがこの集団行動だろう。
1人が遅れれば全員が遅れ、1人のミスが全員のミスになる。
だから、1人が怒られるときは合わせて全体も怒られる。
警察学校では連帯責任が基本中の基本。
1人だけ成績が良くても意味はないし、1人だけ素晴らしい行動をしても無意味。
警察学校で生き抜くためには協調性を大切にし、集団行動で周りに迷惑をかけないことが大事になる。
集団行動の大変さを痛感する
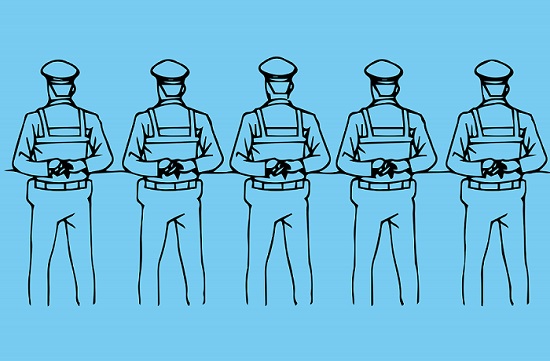
集団行動をするとそれぞれの性格が如実に表れるし、それぞれの人間性もよく分かる。
リーダーシップ・責任感・性格の良し悪しなど、集団行動だからこそ浮き出てくるものがある。
そんな中、警察学校は分単位で行動することが多いため、集合時間や制限時間を決めて行動することがほとんどだ。
時間を守るというのは社会人にとって当たり前のことだが、これが集団生活だとそうはいかない。
明確に時間を設定していも必ず時間を守れない人間が出てくるのだ。
次の行動のために「何時にここに集合」と指示が出ていても平気で守れない者が続出する。
時間を守れない者は準備が遅かったり、単に時間にルーズだったり様々である。
当然ながら誰か一人でも時間に遅れるとクラス全体に迷惑がかかる。
なぜなら全員が揃わないと動けないからだ。
集団行動というのは全員が揃っての行動なので、一人が遅れているならその一人を延々に待ち続ける。
遅れている者を見捨てるという行動はとることができない。
だから警察学校では集団行動についていけない者は干されるし、厳しい扱いを受けることがある。
1人のせいで全員が犠牲になるので、自然とそのような流れになってしまう。
このときもそうだった。
荷物の整理を終え、寮の前に集合するよう指示されたが、時間通りに全員が集まらなかった。
まだこのときは誰も余裕がなく、遅れる者に対して特に気にしなかったが、これが後々に響いてくる。
警察学校において、時間が守れないというのは致命的だ。
時間にルーズな面がある人は十分に気を付けた方がいい。
自分のせいでクラス員を待たせることは申し訳ないし、クラス員から注がれる視線も突き刺さる。
どうしても時間に間に合わないというのは誰にでも起こり得ることだが、なぜだか時間を守れないメンバーはいつも一緒になる。
こうなってしまうとクラスでの立ち位置も危うくなり、追い込まれる原因となる。
「常に誰かと一緒」という生活は想像以上に辛く、精神的にも負担が大きい。
これまでの日常生活と180度違うため、警察学校に入校してからギャップを感じることがほとんどだろう。
”自由な世界に戻りたい”と誰もが思うものだ。
この決断をするのは意外と簡単なのかもしれない。
入校初日に退職者が出た余波はやがて自分のクラスにもやってくることになった。
-続く-
【実録警察学校】第3話「遂に自分のクラスからも離脱者が出る」






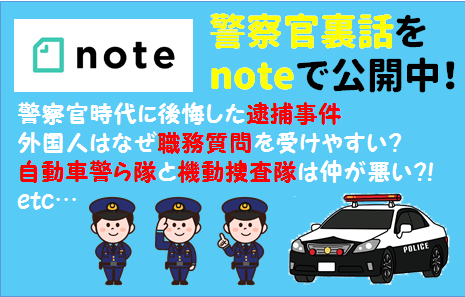



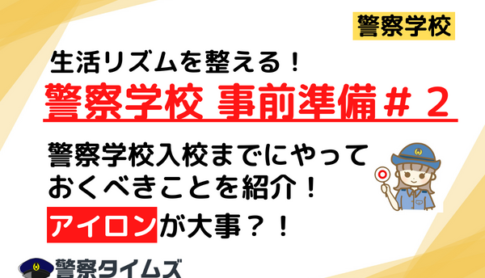

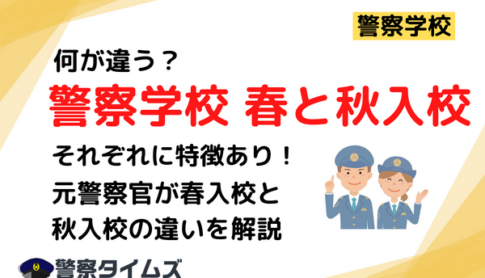


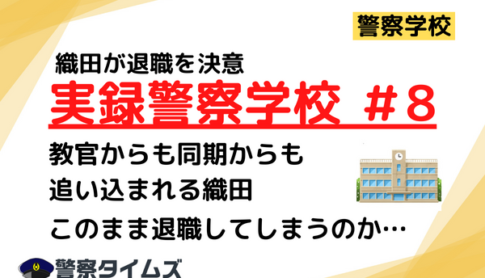
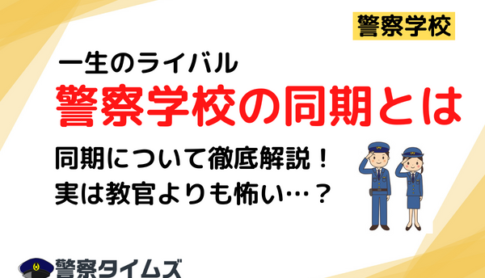
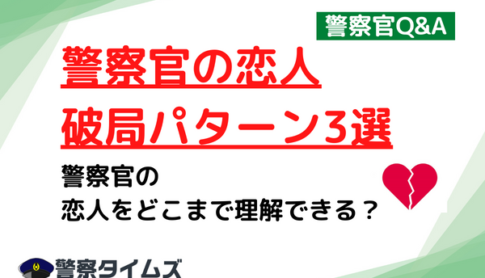
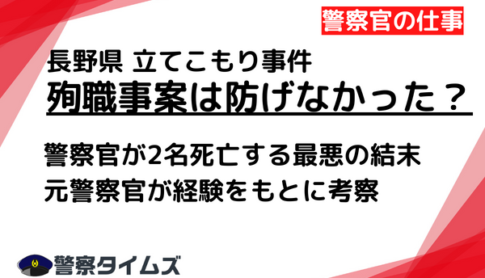
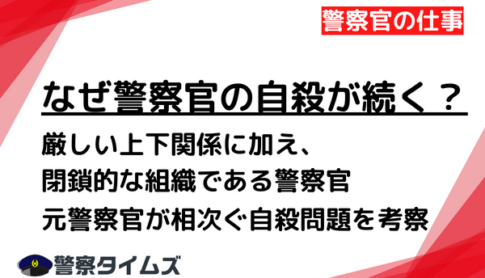
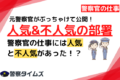
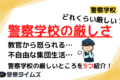
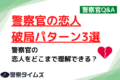
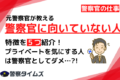

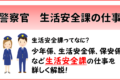

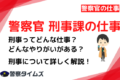
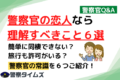
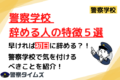

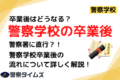
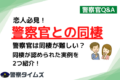
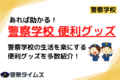
コメントを残す